目次
福井県の美味しいお米
福井の美味しいお米が食べたい!いちほまれ、華越前、福井県産コシヒカリ、大野産コシヒカリ、池田町産コシヒカリ.. 福井県では炊き立てのごはんに「越前蟹味噌バター」で決まり!福井県産の美味しいお米が食べたい!重たいお米は宅配で玄関先まで運んでもらえる便利な通販でお取り寄せ。こちらでは、送料無料でお買い得な福井県の人気米品種、銘柄、ブランド米、新米、玄米をご紹介します。お中元、お歳暮、お祝い、ギフト、贈り物、ふるさと納税、備蓄にもおすすめです。
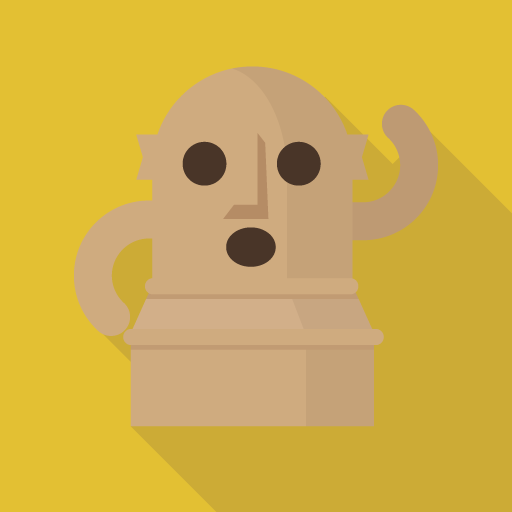
ねえねえおにぎりさん、福井県ではどんなお米が作られているの?
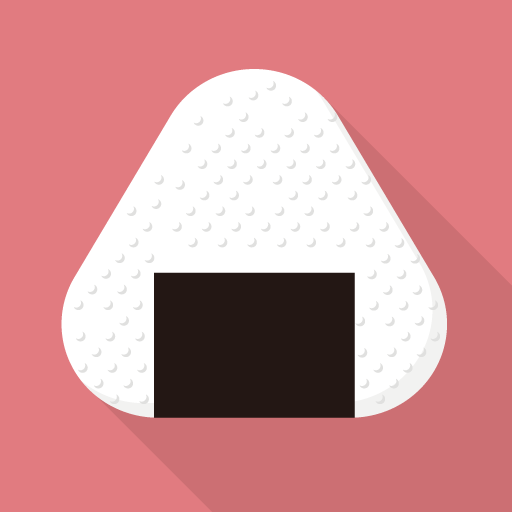
福井県では、いちほまれや華越前、コシヒカリなどが作られているよ。一緒に詳しく調べてみようね!
福井県産の人気銘柄米、ブランド米の種類と特徴
福井県のお米が美味しい理由
福井県はコシヒカリ発祥の地と言われています。
土づくりから差が出る、おいしい福井米。
土づくりと適切な水管理の徹底で、さらなる大粒化を。
稲ワラを早期に鋤込む秋の田起こしと、土壌改良資材の施用割合を向上させることを目標に、土づくりや適切な水管理の徹底による登熱向上(大粒化)を進めています。土壌診断や土壌マップにより現状を把握したうえで、有機入り肥料など土壌改良材の効率的な施用を推進。深耕による根域拡大や幼穂形成期以降の水管理を行い、さらなる登熱向上(大粒化)を促します。栽培技術を徹底し、品質向上を実現。
田植えの時期を徹底して、さらに上質な米に。
コシヒカリは出穂を遅らせる
コシヒカリを5月の連休に移植すると、夏場の高温の時期に出穂します。5月半ば以降に移植し、出穂時期を遅くすることで、高温を回避できます。直播栽培も同様の効果があります。「5月半ばの適期田植え」の成果
平成22年や平成24年など、夏期の高温により全国的に品質が低下した年でも、福井県産コシヒカリは、猛暑による高温傷害の影響も少なく高い1米比率を維持し、過去8年平均は北陸トップの比率です。独自に設けた厳しい基準で福井米の高品質・高食味を確保。
1.9ミリ綱目選別でさらなる粒ぞろいに。
より大粒で高品質なお米をお届けすることを目指して、全福井米を1.9ミリ綱目選別しています。これによりコシヒカリのねばり、味わい、口当たりがさらに良くなりました。日本はもとより、世界を視野に入れた粒ぞろいの福井米をぜひ味わってください。美味しさを守るための工夫があります。
日本屈指のカントリーエレベーター数で品質の高さを保持。
日本屈指の数を誇る34施設において、もみ換算で約9万トンの収容能力を保持。新米とほとんど変わらない品質の保持や、栄養分の損失防止、脂質酸化の抑制、微生物の繁殖や害虫発生の防止などを実施。常に品質の高い貯蔵米をお届けします。
米づくりに最適の自然環境
福井県大野市は、福井県北東部の四囲を山々に囲まれた盆地に位置しま す。
盆地の中心を九頭竜川が流れ、その伏流水によってもたらされる豊富な湧き水で知られています。その湧き水は日本を代表する名水で知られ、御清水(おしょうず)と呼ばれています。名水百選(環境庁選定)にも選ばれ、街のいたるところにある湧水池には毎日多くの人が湧き水を汲みに訪れます。気象は、内陸盆地型の気候で、一日の気温の較差は北陸随一です。夏季に比べ冬季の降水量が多く、冬は比較的長くなり、米づくりには最適の地域といえます。
福井県のお米の収穫量
令和元年度の作付面積: 25,100ha
令和元年度の生産量: 130,500t出典 福井県米穀株式会社公式サイト
この投稿をInstagramで見る
nicolalala68
はらこ飯風ごはん🍚スーパーで魚卵セールに遭遇!
これは…So gooood👍筋子を久しぶりに買ったなら…
美味しいごはんを炊きながら…鮭の西京漬を焼きまして、
銀シャリの上に筋子と乗せただけ。ちょっと豪華に見えますよね(笑)
賞味期限な迫る
瓶詰め栗の甘露煮と🌰
合わせたら秋の食卓。あ、甘じょっぱ効果で、食べちゃう🍚
たまらんです(笑)母の実家が北海道稚内で
漁業を営んでいた事もあり?
子供の頃からいくらより
筋子を食べていました。いつもおにぎりは筋子か、
味噌か、たらこでした〜。思い出のおにぎりの具。
あったら教えてくださいっ🍙筋子に合わせたお米は
#いちほまれ 最高に合う〜🍚ごちそうさまでした🙏
出典 Instagram
いちほまれ
この投稿をInstagramで見る
ysd.ryo
.
今日の朝ごはん
.
今日も美味しい1日を👋
.
#かんのんちのごはん#朝ごはん#朝食#和食#和ごはん#家ごはん#おうちごはん#ビール人妻部#マカロニメイト#タベリー#フーディーテーブル#おうちごはんlover#てづくりごはん365#iegohanphoto#いちほまれ#stayhome#おうち時間を楽しむ#おうち時間出典 Instagram
いちほまれの特徴
コシヒカリのふるさと、福井県からついにコシヒカリを超えた新しいブランド米が誕生しました。
6年をかけて20万種の候補から選ばれたお米です。いちほまれという名前は全国から寄せられた10万件を超える候補の中から選ばれました。
日本一(いち)美味しい、
誉れ(ほまれ)高きお米が由来の通り、豊かなふるさとが育んだ美味しいお米、ご飯の見た目、食感、程よい甘さなど、『新しい美味しさ』を追求しました。
いちほまれの特徴
1.キラキラ輝く白さが食卓を華やかに飾ります。
2.口に含んだ時に、しっとり、ふっくらとした食感に笑顔がこぼれます。
3.さらに噛みしめることで優しい甘さが口の中に広がり、料理の美味しさを一層引き立てます。出典 福井県米穀株式会社公式サイト
通販でお取り寄せ出来るいちほまれ
華越前
この投稿をInstagramで見る
yuu.yoshioka
03/23sat
残り物朝ごはん(あ!ご飯は今朝炊きたてです。) ・赤ワインとホールトマトの煮込みバーグ(ほうれん草、パプリカ、とりバーグの中は玉ねぎと椎茸)
・炊きたて福井産 華越前(シソまぜまぜ空豆乗せ)
・サラダ(サニーレタス、トマト、一口だけ残ってたカレーパン、ポテト、ブロッコリー、コーン、オリーブ)
・コンソメスープ
・リンゴ酢#朝ごはん#ワンプレート#ワンプレート朝ごはん#airkitchen #igersjp #サーモスのフライパンほしい #華越前 #煮込みバーグ
出典 Instagram
華越前の特徴
福井県内では一番早く獲れるお米です。福井生まれの華越前はふっくらとした丸みのあるお米で、特に色の白さと粒ぞろいが特徴です。福井農業試験場が交配・育成した品種で、平成3年に「コシヒカリの前に華が咲く」ことから、「華越前」と命名されました。
出典 福井県米穀株式会社公式サイト
通販でお取り寄せ出来る華越前
福井県産コシヒカリ
この投稿をInstagramで見る
hiroshi.2430
ソースカツ丼細いカツの衣はカリカリ食感。
ソースは甘さのなかにピリッとした辛みがある。
衣にソースの味がしっかり浸透しつつ、カリカリ感のバランス。豚モモ肉が柔らかい。
ご飯はふっくらと炊き上げられ、味噌汁付きがありがたい(^^)
ソースの優しい後味にしばらく余韻が残る。
元祖「ヨーロッパ軒」と人気を二部する福井名物ソースカツ丼の有名店。
街の食堂的な洋食屋の雰囲気が良く、地域に長年根付いて親しまれる人気店だ。
店内には芸能人のサイン入り色紙がズラリと飾られていた。
#福井市グルメ #福井名物ソースカツ丼 #ふくしん #街の洋食屋さん #豚モモ肉 #柔らかい #衣はカリカリ #ソースは自家製 #福井県産コシヒカリ #ご飯はふっくら #地域に根付いたお店 #福井市 #高木中央 #日本式洋食レストラン #ふくいでごはん
出典 Instagram
福井県産コシヒカリの特徴
食味で最高のコシヒカリは福井で生まれ、自然に恵まれた越前平野の土と水により丹精こめて作られました。全国的に幅広く栽培されていて人気も相変わらずナンバーワンです。粘りがあり、香り、味のバランスが最も良いと言われています。国内で一番多く作られ、消費量も多いです。色、ツヤ、味と三拍子揃って炊き上がりの粘りとほのかな甘味が味わえ冷めてもおいしいお米です。
出典 福井県米穀株式会社公式サイト
通販でお取り寄せ出来る福井県産コシヒカリ
大野産コシヒカリ
この投稿をInstagramで見る
uchino_jigoku_paint
『ワンダーズ オブ ネイチャー』
2015年 綿布 アクリル絵具 110×50cm
これは、2015年に大阪市は福島区のお米店・米蔵人おくむらさんから発売された福井県大野産のコシヒカリ2合袋のパッケージ画を担当させて頂いた時の制作前の現地取材で、私が遭遇したちょっと不思議な体験をもとに描いた作品です。
奥村さんと生産者の松田さんに案内して頂いた福井県は大野市、丁( ‘ようろ’と読みます ) の圃場 ( 田んぼ ) は、何と1200年前から京都の醍醐寺の荘園としてすでに米作りが行われていたという大変歴史のある地域で、現在も上下水道はもちろん、電気、ガスのインフラが一切入っていないという極めて清浄が保たれているとんでもない環境でした。そんな場所で、農薬を使わずに米作りを行っておられる松田さんの圃場はホタルの里としても有名で、是非その季節に!とのお招きで我々、6月にお伺いしました。( ちょうどゲンジボタルの最盛期が過ぎ、ヘイケボタルが飛び始めた頃でした。) そうして訪ねた‘ようろ’の圃場は、大野盆地の中のさらに盆地に位置しており、その特異な地形がつくり出す寒暖差がお米の甘さをより増しているとのことでした。夕暮れ前に到着した私達は、松田さんの案内を受けながら段々と陽が落ち始めた圃場を歩きました。丁度梅雨時で、田んぼを取り囲む小さな盆地の小高い山々に霧が追い付けそうなスピードでもくもくと昇っていく中、山の緑と紫に変わっていく空の境界がどんどんぼやけて曖昧になっていく不思議な感覚が心地良かったのをおぼえております。当然、人工光は一切無く、人が管理しているとはいえ、自然が主役の環境は、徐々に存在感を増すカエル達や里山の樹木といった精霊の時間に移り変わって行っている様で、独特な空気が辺りを満たしていくのを肌で感じました。松田さんの説明を聞きながら、森の樹々の間から明滅が確認出来始めたホタルが飛び出すのを待ち、外敵が少ない田んぼの上で雌雄が小さなダンスを舞うのをじっと観ました。( ヘイケボタルはゲンジボタルより体も小さく光も弱いです )
そうしているうちに、ホタルの光だけがきれいに目に映るようになり、足下からあちらこちらと小さな緑の光が際立ち始め、夢中で観察しているうちに私は、奥村さんと松田さんとの距離がかなり離れてしまっていたことに気付いたのです。が、立ち上がって、辺りを見回してもホタルの光以外は真っ暗で、二人の声は聞こえるものの、小さな山々に囲まれた地形のせいか、その方向が全く分かりません。茫洋とした空気がどんどん増していく闇の中、‘うちのさーん’と奥村さんが呼ぶ声が聞こえ、返事をするも、その声が発せられている方向が全く分からないのです。そんな時、私は、何となく声が聞こえた様に感じられた方向にホタルとは違った小さなオレンジ色の明かりを見つけました。それを奥村さんのケータイのLEDだと思った私は、そちらに向かって歩いたのですが、近づくにつれ、そこに誰もいない事に気付き、何となく違うものに誘われてるかな・・と思って、反対に引き返すと二人に落ち合えました。 一帯を満たした雰囲気が独特で、不思議と恐怖とは違った深い感覚でしたが、二人と話すと急に現実に帰ったような明るさに一気に先程までの感覚が無くなっていたのが不思議でした・・。 そうして大阪の日常に戻り、自宅で松田さんのお米を炊いた時、鍋から立ち上る湯気と香りの向こうにあの大野の風景が浮かぶ気がしてこの絵を描きました。後日、松田さんに訊ねたり、山岳関係の本を読んだりしてみると、狐火というものが存在していて、一説によると、遭遇すると吉兆とされるとの話もありましたが、私が見たのがそれなのかは分かりません。松田さんは悪いもんじゃ無いとおっしゃってましたが、全ては闇の中、知るは森の精、もののけ達だけであります・・。 #福井県大野市 #大野産コシヒカリ #無農薬米 #ホタル #ゲンジボタル #ヘイケボタル #狐火 #提灯 #炊飯 #土鍋 #organicrice #willothewisp #lantern #acrylic #acryliconcanvas #painting #contemporarypainting #contemporaryart #art #米蔵人おくむら
出典 Instagram
大野産コシヒカリの特徴
福井県大野市は、福井県北東部の四囲を山々に囲まれた盆地に位置します。気象は内陸盆地型の気候で、一日の気温の較差は北陸随一です。夏季に比べて冬季の降水量が多く、冬は比較的長くなり、米づくりには最適の地域といえます。このような自然に恵まれた地域で育てられた地域限定のお米です。こだわりのお米を希望される方にお奨めできるピッタリのお米です。是非一度お試し下さい。
出典 福井県米穀株式会社公式サイト
通販でお取り寄せ出来る大野産コシヒカリ
池田町産コシヒカリ
この投稿をInstagramで見る
riceshop_sugiyama
今日こ朝食は、七草粥。と言っても材料がなくスズナ(カブの葉)、ススシロ(大根葉)にブロッコリー、ネギなど。
正月は、休肝日がなかったのでしばらく禁酒です。
#七草粥
#池田町産コシヒカリ
#休肝日が必要出典 Instagram
池田町産コシヒカリの特徴
足羽川の源流、水がきれいな池田町で作られた”生産者限定”のコシヒカリです。
出典 福井県米穀株式会社公式サイト
通販でお取り寄せ出来る池田町産コシヒカリ
福井県のごはんのおかず、お供
越前蟹味噌バター
この投稿をInstagramで見る
akemi0420
こないだテレビで見て気が大きくなってたのか、衝動買いした越前蟹味噌バターが届きました。
1ヶ月以上待ちました。すっかり忘れた頃に到着。
とりあえず、熱々ご飯で蟹味噌バター醤油ご飯。目玉焼きと韓国海苔を乗せて、、、
もう、すっごい美味しかったです。笑っちまう美味しさ。
あと、2瓶あるので
次はパスタかなー!!
#越前蟹味噌バター #越前蟹味噌バター醤油ご飯目玉焼き乗せ韓国海苔パラパラ#買って後悔なし#すっごい美味しい出典 Instagram
越前蟹味噌バターとは
「越前蟹味噌バター」は福井県で越前漁港の大貴丸のみが唯一漁を行っている越前産紅ズワイガニの蟹味噌を使ったバターです。 その貴重な蟹をすぐに浜ゆでした後、丸2日以上煮詰めた濃厚な蟹味噌に、バター、調味料などを当社独自のブレンドで特製バターに仕上げました。
蟹は好きだけど蟹味噌はそれほど好きじゃないという方、蟹味噌は磯の匂いが強過ぎてそのままでは食べずらいという方、小さい子供から、高齢者まで食べやすいソフトな味に仕上げました。そのままパンにつけても美味しいですが、オーブン等で軽く焼き上げると又格別です。カニ味噌の美味しさそのままに濃厚で上品な大人の味。 パスタとの相性も抜群です。
出典 楽天市場
通販でお取り寄せ出来る越前蟹味噌バター
お米のこと、もっと知りたい!
お米が出来るまで
3月 種の準備
種をえらぶ
よいお米をつくるには、よい種をえらぶことから始まります。
お米の種「種もみ」は、中身がたっぷりつまった重い粒が、丈夫に成長する強い種と言われています。
中身のつまった重い粒と、そうでない粒を見分けるのに、塩水を使います。中身のつまっていない軽い粒は浮いてきてしまうので、沈んだものだけを選びます。種を消毒する
塩水選を済ませた種もみはよく洗ってから袋に小分けされます。
種についている、様々な稲の病気の病原菌を殺すため、消毒します。
薬剤を使った方法や、60℃の温水に浸けて殺菌する方法があります。種に水分を吸収させる
水槽に種もみ袋を沈め、芽が出るのに必要な水分を2週間位かけて吸収させます。温度管理をして、いっせいに芽を出させます。
4月 苗を育てる/土をつくる
種をまく
育苗箱という苗を育てる箱に、加えた床土と肥料を詰め、播種機を使って、芽出しをした種を均一にまきます。
まいた後はうすく土をかぶせます。苗を育てる
育苗箱はビニールハウスやビニールでおおったトンネルで育てられます。昼と夜の温度差を管理したり、土の水分を調整して大事に大事に育てます。
田んぼの土をつくる
田んぼの土をトラクターでたがやし、やわらかく掘りおこして田植えにそなえます。
土の性質によって、肥料をまいて良い土をつくります。5月 田植え
田に水を入れる(代かき)
田に水を入れ、土がトロッとするまで、ロータリーという機械でかきまぜながら、土の表面が平らになるようにならしていきます。
これを「代かき」といいます。田植え
田植え機を使って、まっすぐ、むらなく苗を植えます。機械で植えられない所は、手作業で植えます。昔は家族みんなで数日かけて、手で植えていました。
6月 稲を育てる
生育調査
稲の背丈や葉の枚数、葉の色などを調べ、成長の具合を確認し、今後の管理の計画を立てます。
水管理・防除
田の水が少なくなったら水を足し、多すぎる時は水門を開けて水を抜いたり、きめ細やかに水量を調整します。
また、防除と呼ばれる害虫や雑草から稲を守る日々が続きます。田に溝を掘る
稲の根が土の中でのびのびと養分や水分を吸収できるよう、稲と稲の間に溝を掘ります。これを作溝(さっこう)といいます。
この溝によって水管理もしやすくなります。7月 稲を育てる
中干し
稲がある程度育つと、田んぼの水を抜いて土を乾かし、稲の根を空気にふれさせ、土に酸素を補給させます。
これが「中干し」という作業です。
稲穂の出る時期になると、数日おきに水を抜いては入れる作業をします。肥料をあたえる
田の稲が均一に成長するように、状態を見ながら適時肥料をあたえます。
田植えの後に肥料を追加することを追肥(ついひ) といいます。
チッソ、リン酸、カリウムなどが米づくりに必要な成分です。8月 稲を育てる
虫や病気から守る
気温が上がる時期には、稲の大敵いもち病をはじめ、さまざまな病気や害虫が発生します。
地域別に定められた防除基準に沿って対策がとられ、無人ヘリによる薬剤の散布などが行なわれます。9月 収穫
稲刈り
黄金色の稲穂が垂れるようになると稲刈りの時期がやってきます。
一般的に稲刈りは、コンバインと呼ばれる刈り取りと脱穀(稲からもみだけをとる)を同時にできる機械が使われます。10月 収穫
もみを乾燥させる
刈り取られた稲は乾燥機にかけます。
乾燥機を持たない農家ではカントリーエレベーター(大規模乾燥・一時保管施設)に持ち込みます。20%以上の水分を含んでる稲が腐ってしまわないように15%前後まで熱風をあてて乾燥していきます。
急に乾燥すると「胴割れ」といって米にひずみが生じ割れてしまいますのでゆっくりと乾燥していきます。玄米にする
乾燥したもみは、もみすり機で周囲の殻をとり、玄米に加工します。
検査・等級検査
選別機(ライスグレーダー)をとおし、くず米と出荷用の玄米に選別します。多くの場合、JA(農協)を通して、検査員が品質チェックを行い1等、2等などランク付けされ、出荷されます。
出典 全農パールライス公式サイト
JAバンクアグリ・エコサポート基金様の動画 「米ができるまで」
米ができるまでを作業工程順に追い、さまざまな作業や、稲作農家の工夫や努力を紹介しています。ぜひご覧ください!
美味しいお米の炊き方
お米を研ぐ。 ぬかの洗浄がおいしさを左右する
お米には、玄米を精白したときに出る「ぬか」が付着しています。精白技術がすすんだ現在は、昔ほどではなくなりましたが、このぬかを十分に取り除くかどうかが、ご飯の味を左右します。お米の研ぎ方が、おいしさの第一につながります。
最初はたっぷりの水で素早くすすぎ、あとは少量の水に浸し、手のひらで押すようにして研ぎます。基本的には冷たい水で研ぎますが、冬場など、寒いからといってしゃもじなどを使って研ぐよりは、ぬるま湯を使って手で研ぐようにしましょう。また、冬場は乾燥による静電気により、ぬかの付着が多くなりますので、洗いを1回分多くすると良いでしょう。お米の量を計る。基本はすりきり一杯で
お米も水も、正確に計ることが大切です。お米はカップに対し、すりきりでピッタリと計るように心がけましょう。水は、米重量の1.2倍が基準です。あとは好みに合わせて増減して硬さを調整しますが、固めにしたいからといって極端に水を減らしたり、柔らかくしたいからといって極端に水を増やしてはダメです。微妙な水加減で慎重に…!
また、ご飯は炊く量によって味が相当に異なってきます。できれば大きなお釜にいっぱい炊くのが理想的で、炊く量に応じて釜の大きさを使い分けると良いでしょう。お釜や炊飯器で炊ける量をいっぱいに炊くようにすると、おいしいご飯になります。(釜に対して8割が最大量です。)
お米を水に浸す浸漬。ふっくらと炊きあがるコツ
炊く前に、水に浸すことがとても大切です。浸漬をすることにより、お米の芯までたっぷりと水が浸透します。 水を含んだお米は、炊き増えし、ふっくらと炊き上がります。最低30分(冬場なら1時間)浸漬するようにしましょう。
また、お米は水を含む量に限りがあるため、長く漬けすぎると逆にデンプン層が流出してベタつきの原因になってしまいます。 最長でも90分が目安となります。浸漬の際は、温度が低いほうが好ましいので、夏場などは冷蔵庫に入れておくと、なお良いでしょう。おいしさ、栄養面でも必須の蒸らし。加減が大切なポイント
炊き上がったご飯は、充分に蒸らすことが必要です。ご飯は、蒸らし加減でも味がずいぶん違ってきます。火を止めてから10~15分間は、フタをとらずにそのまま蒸らします。 蒸らしすぎてもご飯が絞まってしまうので要注意。
火を止めた直後のご飯と、充分に蒸らしたご飯を比べると蒸らしたご飯は ふっくらとして見た目にもおいしそうです。これは蒸らす段階で、お米に充分蒸気を吸いこませ、 余分な水分がお釜の中に残らないようにしているからです。そのためには、釜の中は火を止めたときのままの高温状態にしておくことが望ましいのです。さらに、充分な蒸らしをすることで、米の中心のデンプンを消化吸収しやすい状態にもしてくれます。
味を均一化するシャリきり。風味を保つ秘訣
蒸らしが終わったら、釜の底からお米をはがすようにかき混ぜます。
しゃりきりをすることにより、釜の底や中のお米が空気に触れ、余分な水分を飛ばすことができます。また、味も均一化され、風味を損なわず保温できます。
米を立たせるようにシャリきりしましょう!出典 米福公式サイト
動画 家庭での美味しいご飯の炊き方
こちらの動画で、お米の保管方法、計り方、研ぎ方、水加減、ほぐし方などの基本を学ぶことが出来ます。
精米の度合にもこだわってみたい!
白米
一般的に食べられている白いお米です。食べやすく美味しいのが白米です。玄米
慣れないと食べにくいボソボソとした食感ですが、栄養価が一番あります。3分づき
栄養や食物繊維がかなり含まれてますが、食感はボソボソします。5分づき
白米と玄米の中間で、栄養と食物繊維は十分あります。食感は少しボソボソします。7分づき
食べやすく栄養価もあり、初めて分づき米を食べる方におすすめです。出典 丸吉 茅野商店公式サイト
日本全国の美味しいお米 Japanese rice
福井県の美味しいもの、もっと知りたい!
福井県の食卓
お米
牛肉
豚肉
鶏肉
福井県産の銘柄鶏肉の種類と特徴
フルーツ、果物
福井県産のフルーツ、果物の種類と特徴
スイーツ、お菓子
日本酒、地酒
地ビール、クラフトビール
Red Doorsが運営するサイト












