目次
山形県の美味しいお米
山形の美味しいお米が食べたい!つや姫、はえぬき、雪若丸、亀ノ尾.. 山形県では炊き立てのごはんに郷土料理「だし」で決まり!山形県産の美味しいお米が食べたい!重たいお米は宅配で玄関先まで運んでもらえる便利な通販でお取り寄せしたい。こちらでは、送料無料でお買い得な山形県産の人気米品種、銘柄、ブランド米、新米、玄米、無洗米をご紹介します。お中元、お歳暮、お祝い、ギフト、贈り物、ふるさと納税、備蓄にもおすすめです。
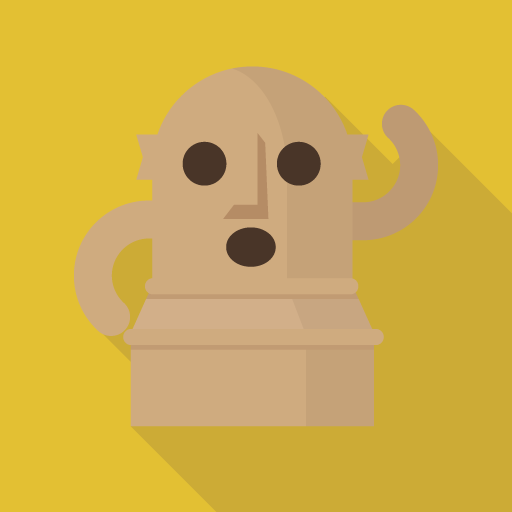
ねえねえおにぎりさん、山形県ではどんなお米が作られているの?
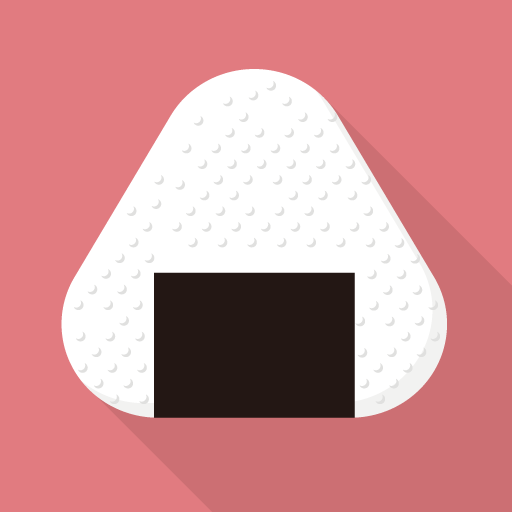
つや姫やはえぬき、雪若丸に亀ノ尾などが作られているよ。一緒に詳しく調べてみようね!
山形県産の人気銘柄米、ブランド米の種類と特徴
令和元年度の作付面積:64,500ha
令和元年度の収穫量:404,400t
つや姫
この投稿をInstagramで見る
chacky1124
今年の節分は
友達のご主人윤(ユン)家伝統のレシピを教えてもらって、김밥(キムパ)を作りました♪お米は、山形の「つや姫」❤️
形はイマイチだけど、自分でも美味しくできたと思う。
家族もパクパク食べてくれて、あっという間に完売😊
嬉しかったから、また作りたいと思います💕#김밥#キムパ#海苔巻き#韓国グルメ#山形米#つや姫#おいしい山形2022新春#koreanfood#おうちごはん#ごはん記録#畑のほうれん草#もかさんハピバ🎂
出典 Instagram
つや姫の特徴
全国を驚かせた極上食味「つや姫」
誕生以来連続「特A」獲得コシヒカリを超える総合評価で2010年デビュー
山形県は四季の変化が鮮やかで、山間部の冬の豪雪はそのまま山に貯えられ、やがて豊かな湧き水となって水田を潤す。夏は過去に国内での最高気温を記録するほど高温となる。肥沃な土壌に加え、年間・昼夜の温度差が大きく、稲作には最適な条件を備えた適地として広く知られてきた。
そして近年、山形米の名声を一気に高めたのが、2010年秋にデビューした県産ブランド米「つや姫」。誰もが認める「美味しい米」と、反響を呼んだのだ。
まだ世に出る前の2007年、(財)日本穀物検定協会が、つや姫(当時は山形97号)の食味官能試験を実施。外観や味などについて「艶がある・粒がそろっている・白い・甘みがある・うまみがある・口あたりがよい・粒がしっかりしている」などのコメントを出す。その試験は、「コシヒカリ」と比較する形で行われ、総合評価でつや姫が上位にランク。また県農業総合研究センターによる食味官能試験でもコシヒカリや他の米を上回る結果を打ち出したのである。
つや姫誕生に至るまでには、長い米づくりの歴史があった。山形県の稲作は明治10年代から近代化が始まり、昭和初期には栽培技術も向上し、10a当たりの収量が、全国平均を大きく上回るようになる。県農業試験場の設立もあって、官民一体の取組みが早くから機能していた。山形が産んだ名品種「亀の尾」のうまさを継ぐ
1893年、庄内町(旧余目町)の阿部亀治氏が育成した米の新品種「亀の尾」が発表され、安定多収・良質良食味とあって全国に普及。大正期には「神力」「愛国」とともに日本三代品種に数えられた。特に食味の評価が高く、後に多くの品種改良の交配親となる。現在人気のコシヒカリも亀の尾がルーツだ。
山形県では1992年、亀の尾をルーツとする「はえぬき」をデビューさせたところ、またたく間に主力品種となった。しかし次第にコシヒカリが全国を席巻するようになると、県内生産者からは、「もっと美味しい米、味も品質もコシヒカリを超える米を作ってほしい」との声があがってきた。
そこで県では1998年、農業試験場庄内支場(現農業総合研究センター水田農業試験場)において新品種つや姫の開発に着手する。ともにコシヒカリ系の、父「東北164号」と母「山形70号」を交配して育成。開発を急ぐために、世代促進ハウスを暖房し、冬期間も栽培を続けたという。また、ほ場での栽培では、稲を一株ずつ植え毎日細かくチェックし、病気に強いもの、収量が多く獲れそうな株の選抜を繰り返した。そして育成世代の早い段階から、実際にご飯を炊いて食べ比べ、食味の良さを追求。こうして、10万分の1の確率で選抜されたつや姫が、あの亀の尾の良食味性を受け継いで誕生した。
栽培特性は草丈が短いため倒伏に強く、登熟も良い晩生種。特筆すべきは、やはり食味の良さだ。「粒の大きさ」、「白い輝き」、「旨さ」、「香り」、「粘り」等は先述の通り。日本穀物検定協会の2017年産米の食味ランキングも最上級の特A評価となり、デビュー年から連続で獲得している。出典 おいしい山形推進機構事務局公式サイト
通販でお取り寄せ出来るつや姫
はえぬき
この投稿をInstagramで見る
opeko_natto
粒立ち抜群♪はえぬき🌾
.
山形の納豆に続き
今回はお米を。
.
つや姫や雪若丸、そして今回の「はえぬき」
.
はえぬきは米の食味ランキングにおいて22年連続で特Aに認定されてるそう。
この他にも22年以上認定されているお米は、魚沼産コシヒカリのみだと言うから、このお米何気に凄い。
.
大粒のはえぬきは炊きあがりは一粒一粒がしっかりしている。
甘さを抑えたあっさりとした味わいで、朝や和食に合うイメージ。塩気あるおかずにも合うと思うし、
甘めのタレの納豆とも相性がいい。
個人的には大粒のごはんは大粒の納豆で食べたくなるなー
.
粒立ちもよくしっかりしてるので
カレーや卵かけご飯などとも相性良いはず。
いや、間違いなくいいだろな。
.
冷めてもベチャッとなりにくいので
夏場のお弁当にもオススメです。
.
.
お米も色々食べ比べてみると
納豆と同じで一つ一つに個性があって面白い。
.
次はどれ食べようかなー!
.
ご飯#炊きたてご飯#米#お米#美味しいお米#食器#茶碗#美味しいもの#朝ごはん#おうちごはん#washoku#和食#はえぬき#山形のお米 #農業 #rice出典 Instagram
はえぬきの特徴
平成をリードしてきたはえぬきも、まだまだ現役だ。つや姫同様、県の庄内支場が「庄内29号」と「あきたこまち」を交配して研究・育成。当時の最高の食味、倒伏や病気に負けない安定的な収量性、絶対的な品質の高さを持つ『ユメのコメ』として誕生した。
食味は米粒の張りがしっかりしていて粘りもあり、歯ごたえが良い。噛むほどに旨み・甘みが口の中に広がり、冷めても美味しさが変わらない。はえぬきは現在も県全体の作付面積の6割強を占めており、業務用としても人気が高い。出典 おいしい山形推進機構事務局公式サイト
通販でお取り寄せ出来るはえぬき
雪若丸
この投稿をInstagramで見る
nicolalala68
おにぎり、卵焼きに豚汁🍙柚子大根とぬか漬け添えて。
最高のラインナップで
ごちそう朝ごはん😭💕
⚪︎明太子おにぎり🍙
⚪︎梅干しおにぎり🍙
⚪︎ひじきおにぎり🍙
⚪︎牛そぼろ、きんぴらごぼう入り卵焼き
⚪︎具沢山豚汁
⚪︎ぬか漬け 柚子大根
ごはんは、山形県の雪若丸に
オーツ麦と昆布、キパワーソルト、
香りのないココナッツオイルを入れて炊きました🍙✨ロゴとパッケージがかわいい☺️👌
お茶碗に乗ったてんこ盛りのごはん🍚
4つでデザインされているんだね。一粒一粒が主張する感じで
混ぜごはんにも相性良かった🍙それにしても、梅干しの大きさ💦
以前は小梅もあったの😂
また小梅、売って欲しいなぁ〜
本日の目標!
リビング他のカーテン洗濯(これ重労働)
年賀状の宛名書き。
既に腕が筋肉痛ですが😂
しっかり食べて
今日も頑張りますっ💪😤
#雪若丸 #山形県出典 Instagram
雪若丸の特徴
ロングセラー「はえぬき」期待の新品種「雪若丸」
そしてもう一つ、2018年秋デビューの県オリジナル新品種「雪若丸」にも注目したい。「山形80号」と「山形90号」を交配して育成。倒伏に強いうえ、高温やいもち病にも強く、栽培しやすい特性を持つ。
しっかりとした粒感と適度な粘りが両立した新食感で、あっさりと上品な味わい。炊いた時の白さや光沢も美しく、つや姫の凜々しい弟分として、期待を一身に集めている。出典 おいしい山形推進機構事務局公式サイト
通販でお取り寄せ出来る雪若丸
亀ノ尾
この投稿をInstagramで見る
日本酒好きには「亀ノ尾(原種)」と聴けば知らない人は居ないほど。
実は、ブランド品種の「コシヒカリ」や「ひとめぼれ」、「あきたこまち」、「つや姫」の御先祖様なのです。#亀ノ尾#日本酒
出典 Instagram
亀ノ尾の特徴
明治26年(1893年)9月29日、山形県の篤農家・阿部亀治は運命の出会いをします。
立谷沢村(現.庄内町)中村集落にある熊谷神社に、小出新田の人達と御参りに行ったとき、付近の水田の水口(水の取入口)に植えられていた「惣兵衛早生(冷立稲)」の中から、倒伏せず起立した3本の穂を目にします。その優れた穂を水田の持ち主にお願いし、貰い受けて持ち帰ることにしました。(この稲は、遺伝学的には自然突然変異の可能性が強いと言われています。)この時、一緒に行った人達、水田の持ち主も、この持ち帰った3本の穂が、後世まで影響を与える特別な品種につながるなどとは思いもしなかったことでしょう。
【逸話】亀治が熊谷神社参拝の折、仏のお告げを聞き、示唆された場所へ足を運んだところ、その水田にたどり着いたとも言われています。
亀治は持ち帰った籾をもとに、翌年の明治27年(1894年)から作付けを始めます。他の品種と比較するため「大野早生」「月布」「千葉錦」等とともに植えました。しかし、この年は肥料を入れすぎたため、全部倒伏してしまいました。
翌年の明治28年(1895年)も、肥料をセーブしていたにも係わらず全部倒伏させてしまい、肥料の影響だけではないことに気付きます。さらに明治29年(1896年)には、間断灌水を行い、朝夕は深水、昼は浅水にして、水温と地温を上げる工夫を試みましたが倒伏。
明治30年(1897年)となり、この年は春から天候不純で害虫の「ウンカ」が発生します。しかも、冷害の年でした。しかし、研究成果が出たのか、倒伏せずに収穫することに成功します。 この年、全国平均が1石1斗8升(約177キログラム)であったのに対し、この品種(当時まだ名前が付いていない)は2石(約300キログラム)の収穫でした。周囲の農民は大いに驚いたことでしょう。倒伏して失敗した年でも、優れた穂だけを抜き取るなどの努力をし、その当時小出新田の農民の注目を受けていました。
友人であった太田頼吉は、この水稲種に亀治の一字を取り「亀ノ王」と命名するように推めましたが、亀治は、「王」ではおこがましいから「尾」でよい、ということで、試作品種に「亀ノ尾」と命名しました。亀治31歳のことでした。亀治は優秀な「穂」だけを、欲しいと訪れた方や農民に無料で配りました。
この「亀ノ尾」は、当初は早生品種に分類されていましたが、その後品種の出穂期が総じて早くなったため「中生種」として分類されました。性質としては「耐冷性品種」で、米質・食味がよく、少ない肥料でも生育量(長稈)が大きく、分けつも中位。ただし、耐病性は弱かったのですが、収量は他の品種に比べると俄然多いのです。「亀ノ尾」の種子が出回り始めた明治30年代は、稲作技術の革新期にあたり、乾田馬耕(かんでんばこう)や堆肥改良(たいひかいりょう)、塩水選等が実行に移されていました。このような新しい技術導入の波に乗って新品種としてデビューしたのでした。しかも亀治は、「亀ノ尾」を他の品種と無料で交換し、種の純粋を守ることと、種の劣化を防ごうとしながら、普及に努めました。亀治の人柄を表しています。
この頃、庄内平野で栽培されていた稲は、晩熟(ばんじゅく)の稲が多く、冷害の危険率が非常に高く、施肥方法も、堆肥・大豆粕等を基肥として施す、という栽培方法でした。この少量施肥が「亀ノ尾」栽培に幸いしたのでした。
こうした条件のもとで「亀ノ尾」の出現は、まさに時代の申し子のようなものでした。またたく間に県内に広がり、県内で一番多かった大正2年で47,438ヘクタールもの面積で栽培されました。また、全国から朝鮮半島にも広がり、大正14年には栽培面積194,914ヘクタールにもおよび、「神力(しんりき)」「愛国(あいこく)」とともに、日本水稲優良三大品種(にほんすいとうゆうりょうさんだいひんしゅ)に数えられました。
このように、「亀ノ尾」の特性は時代にマッチし、明治40年より大正6年頃までの主流品種として栽培され、購入肥料である、大豆粕、魚粕等有機肥料中心の施用にあっては、充分増収してきました。しかし、大正7年以降、石灰窒素や硫安などの無機質肥料(むきしつひりょう)の施用がさかんになり始めると、「亀ノ尾」の特性「耐病性」に弱く、長稈であることが、多肥料栽培時代に入っては「倒伏」しやすく、耐肥性に劣ることから、豊国や大野早生・イ号にその位置を譲ることになります。「亀ノ尾」は「酒造米(しゅぞうまい)」にも適し、味付け米として根強い需用もあり、その後も一定の面積に栽培が続いています。
今日、経済栽培としての作付けは途絶えましたが、漫画「夏子の酒」(講談社モーニングKC/尾瀬あきら著)の中でも、幻の米のモデルとなるなど、近年になって自然指向の波に乗り、醸造家により自家栽培され、「吟醸酒(ぎんじょうしゅ)」として生まれ変わり、幻の酒として全国に広まりつつあります。
平成9年には、旧余目町(現・庄内町)において、創造ネットワーク、酒造・酒販の方々の協力のもと、「第1回亀ノ尾サミット」が開催され、全国の「亀ノ尾」で造られた自慢のお酒を持ち寄っての賞味の集いが行われました。平成18年、仙台会場の第10回サミットをもって終了しましたが、今後も酒造米としての「亀ノ尾」の人気は衰えることはないでしょう。出典 庄内町役場公式サイト
山形県のごはんのおかず、お供
山形のだし
この投稿をInstagramで見る
mikason925
2019.07.03水曜日
・
夜ごはん、というかつまみのひと品
・
#山形のだし
・
安くて美味しい
きゅうりと茄子が手に入ったので
今年2回目の #だし
山形の義伯母直伝のレシピ
・
あーるもんなんでも
こめくして混ぜればいいんだじー
って教わった笑
・
今日は
きゅうり、茄子、おくら、納豆昆布
大葉、茗荷、長葱、おかか、醤油
*
*
#夜ごはん #夜ご飯 #夕食 #dinner #うちごはん #おうちごはん #手料理 #料理写真 #和食 #暮らし #日々 #おうち居酒屋 #晩酌 #つまみ #おつまみ #IG呑んべえ部 #foodpic #instafood #yammy #japanesefood #マカロニメイト #フーディーテーブル #IGersJP出典 Instagram
通販でお取り寄せ出来る山形のだし
お米のこと、もっと知りたい!
お米が出来るまで
3月 種の準備
種をえらぶ
よいお米をつくるには、よい種をえらぶことから始まります。
お米の種「種もみ」は、中身がたっぷりつまった重い粒が、丈夫に成長する強い種と言われています。
中身のつまった重い粒と、そうでない粒を見分けるのに、塩水を使います。中身のつまっていない軽い粒は浮いてきてしまうので、沈んだものだけを選びます。種を消毒する
塩水選を済ませた種もみはよく洗ってから袋に小分けされます。
種についている、様々な稲の病気の病原菌を殺すため、消毒します。
薬剤を使った方法や、60℃の温水に浸けて殺菌する方法があります。種に水分を吸収させる
水槽に種もみ袋を沈め、芽が出るのに必要な水分を2週間位かけて吸収させます。温度管理をして、いっせいに芽を出させます。
4月 苗を育てる/土をつくる
種をまく
育苗箱という苗を育てる箱に、加えた床土と肥料を詰め、播種機を使って、芽出しをした種を均一にまきます。
まいた後はうすく土をかぶせます。苗を育てる
育苗箱はビニールハウスやビニールでおおったトンネルで育てられます。昼と夜の温度差を管理したり、土の水分を調整して大事に大事に育てます。
田んぼの土をつくる
田んぼの土をトラクターでたがやし、やわらかく掘りおこして田植えにそなえます。
土の性質によって、肥料をまいて良い土をつくります。5月 田植え
田に水を入れる(代かき)
田に水を入れ、土がトロッとするまで、ロータリーという機械でかきまぜながら、土の表面が平らになるようにならしていきます。
これを「代かき」といいます。田植え
田植え機を使って、まっすぐ、むらなく苗を植えます。機械で植えられない所は、手作業で植えます。昔は家族みんなで数日かけて、手で植えていました。
6月 稲を育てる
生育調査
稲の背丈や葉の枚数、葉の色などを調べ、成長の具合を確認し、今後の管理の計画を立てます。
水管理・防除
田の水が少なくなったら水を足し、多すぎる時は水門を開けて水を抜いたり、きめ細やかに水量を調整します。
また、防除と呼ばれる害虫や雑草から稲を守る日々が続きます。田に溝を掘る
稲の根が土の中でのびのびと養分や水分を吸収できるよう、稲と稲の間に溝を掘ります。これを作溝(さっこう)といいます。
この溝によって水管理もしやすくなります。7月 稲を育てる
中干し
稲がある程度育つと、田んぼの水を抜いて土を乾かし、稲の根を空気にふれさせ、土に酸素を補給させます。
これが「中干し」という作業です。
稲穂の出る時期になると、数日おきに水を抜いては入れる作業をします。肥料をあたえる
田の稲が均一に成長するように、状態を見ながら適時肥料をあたえます。
田植えの後に肥料を追加することを追肥(ついひ) といいます。
チッソ、リン酸、カリウムなどが米づくりに必要な成分です。8月 稲を育てる
虫や病気から守る
気温が上がる時期には、稲の大敵いもち病をはじめ、さまざまな病気や害虫が発生します。
地域別に定められた防除基準に沿って対策がとられ、無人ヘリによる薬剤の散布などが行なわれます。9月 収穫
稲刈り
黄金色の稲穂が垂れるようになると稲刈りの時期がやってきます。
一般的に稲刈りは、コンバインと呼ばれる刈り取りと脱穀(稲からもみだけをとる)を同時にできる機械が使われます。10月 収穫
もみを乾燥させる
刈り取られた稲は乾燥機にかけます。
乾燥機を持たない農家ではカントリーエレベーター(大規模乾燥・一時保管施設)に持ち込みます。20%以上の水分を含んでる稲が腐ってしまわないように15%前後まで熱風をあてて乾燥していきます。
急に乾燥すると「胴割れ」といって米にひずみが生じ割れてしまいますのでゆっくりと乾燥していきます。玄米にする
乾燥したもみは、もみすり機で周囲の殻をとり、玄米に加工します。
検査・等級検査
選別機(ライスグレーダー)をとおし、くず米と出荷用の玄米に選別します。多くの場合、JA(農協)を通して、検査員が品質チェックを行い1等、2等などランク付けされ、出荷されます。
出典 全農パールライス公式サイト
JAバンクアグリ・エコサポート基金様の動画 「米ができるまで」
米ができるまでを作業工程順に追い、さまざまな作業や、稲作農家の工夫や努力を紹介しています。ぜひご覧ください!
美味しいお米の炊き方
お米を研ぐ。 ぬかの洗浄がおいしさを左右する
お米には、玄米を精白したときに出る「ぬか」が付着しています。精白技術がすすんだ現在は、昔ほどではなくなりましたが、このぬかを十分に取り除くかどうかが、ご飯の味を左右します。お米の研ぎ方が、おいしさの第一につながります。
最初はたっぷりの水で素早くすすぎ、あとは少量の水に浸し、手のひらで押すようにして研ぎます。基本的には冷たい水で研ぎますが、冬場など、寒いからといってしゃもじなどを使って研ぐよりは、ぬるま湯を使って手で研ぐようにしましょう。また、冬場は乾燥による静電気により、ぬかの付着が多くなりますので、洗いを1回分多くすると良いでしょう。お米の量を計る。基本はすりきり一杯で
お米も水も、正確に計ることが大切です。お米はカップに対し、すりきりでピッタリと計るように心がけましょう。水は、米重量の1.2倍が基準です。あとは好みに合わせて増減して硬さを調整しますが、固めにしたいからといって極端に水を減らしたり、柔らかくしたいからといって極端に水を増やしてはダメです。微妙な水加減で慎重に…!
また、ご飯は炊く量によって味が相当に異なってきます。できれば大きなお釜にいっぱい炊くのが理想的で、炊く量に応じて釜の大きさを使い分けると良いでしょう。お釜や炊飯器で炊ける量をいっぱいに炊くようにすると、おいしいご飯になります。(釜に対して8割が最大量です。)
お米を水に浸す浸漬。ふっくらと炊きあがるコツ
炊く前に、水に浸すことがとても大切です。浸漬をすることにより、お米の芯までたっぷりと水が浸透します。 水を含んだお米は、炊き増えし、ふっくらと炊き上がります。最低30分(冬場なら1時間)浸漬するようにしましょう。
また、お米は水を含む量に限りがあるため、長く漬けすぎると逆にデンプン層が流出してベタつきの原因になってしまいます。 最長でも90分が目安となります。浸漬の際は、温度が低いほうが好ましいので、夏場などは冷蔵庫に入れておくと、なお良いでしょう。おいしさ、栄養面でも必須の蒸らし。加減が大切なポイント
炊き上がったご飯は、充分に蒸らすことが必要です。ご飯は、蒸らし加減でも味がずいぶん違ってきます。火を止めてから10~15分間は、フタをとらずにそのまま蒸らします。 蒸らしすぎてもご飯が絞まってしまうので要注意。
火を止めた直後のご飯と、充分に蒸らしたご飯を比べると蒸らしたご飯は ふっくらとして見た目にもおいしそうです。これは蒸らす段階で、お米に充分蒸気を吸いこませ、 余分な水分がお釜の中に残らないようにしているからです。そのためには、釜の中は火を止めたときのままの高温状態にしておくことが望ましいのです。さらに、充分な蒸らしをすることで、米の中心のデンプンを消化吸収しやすい状態にもしてくれます。
味を均一化するシャリきり。風味を保つ秘訣
蒸らしが終わったら、釜の底からお米をはがすようにかき混ぜます。
しゃりきりをすることにより、釜の底や中のお米が空気に触れ、余分な水分を飛ばすことができます。また、味も均一化され、風味を損なわず保温できます。
米を立たせるようにシャリきりしましょう!出典 米福公式サイト
動画 家庭での美味しいご飯の炊き方
こちらの動画で、お米の保管方法、計り方、研ぎ方、水加減、ほぐし方などの基本を学ぶことが出来ます。
精米の度合にもこだわってみたい!
白米
一般的に食べられている白いお米です。食べやすく美味しいのが白米です。玄米
慣れないと食べにくいボソボソとした食感ですが、栄養価が一番あります。3分づき
栄養や食物繊維がかなり含まれてますが、食感はボソボソします。5分づき
白米と玄米の中間で、栄養と食物繊維は十分あります。食感は少しボソボソします。7分づき
食べやすく栄養価もあり、初めて分づき米を食べる方におすすめです。出典 丸吉 茅野商店公式サイト
日本全国の美味しいお米 Japanese rice
山形県の美味しいもの、もっと知りたい!
山形県の食卓
お米
牛肉
豚肉
鶏肉
フルーツ、果物
スイーツ、お菓子
日本酒、地酒
地ビール、クラフトビール
Red Doorsが運営するサイト









